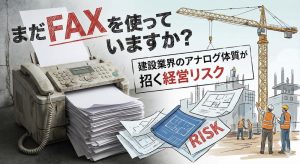「ビル管理の仕事って、具体的に何をするの?」。
そう聞かれたとき、私はいつも「身近なところだと、トイレ清掃をイメージしてみてください」と答えます。
一見、地味で単純な作業に見えるかもしれません。
しかし、実はこのトイレ清掃にこそ、ビル管理の本質がぎゅっと詰まっているんです。
こんにちは。
不動産管理会社で広報や業務改善を担当している、中川紗季と申します。
現場スタッフとして5年、本部で5年勤務した経験から言えるのは、「トイレを見れば、その現場の管理レベルが分かる」ということです。
この記事は、単なる清掃マニュアルではありません。
「誰でも安心して働ける現場」をつくるために、トイレ清掃という日常業務から、どんな“気づき”を得られるのか。
現場と本部の両方を知る私ならではの視点で、お伝えしていきたいと思います。
目次
トイレ清掃に見る“気づき”の視点
なぜトイレ清掃が現場の鏡なのか?
トイレは、そのビルを利用する全ての人が使う可能性がある場所です。
だからこそ、その空間の清潔さや快適さは、ビル全体の印象に直結します。
例えば、床がピカピカでも、トイレットペーパーが補充されていなかったらどうでしょう。
「管理が行き届いていないな」と感じてしまいますよね。
つまりトイレは、清掃の質だけでなく、備品の管理体制や、利用者のマナー、さらには現場スタッフの働きぶりまで映し出してしまう「鏡」のような存在なのです。
小さな違和感に気づく力が管理品質を左右する
「いつもよりゴミ箱からゴミがあふれるのが早いな」。
「なんだか、洗面台の周りが水浸しになっていることが多い」。
こうした小さな違和感に気づけるかどうかが、プロの仕事とそうでない仕事を分けるポイントだと私は考えています。
この違和感の裏には、
「近くでイベントが開催されて、利用者が急増しているのかも」
「ハンドソープの容器が押しにくくて、周りに飛び散っているのかも」
といった、次のアクションにつながるヒントが隠されています。
ただ決められた作業をこなすだけでなく、こうした変化のサインをキャッチする力が、ビル管理の品質を大きく向上させるのです。
利用者目線で見る清掃のチェックポイント
マニュアル通りの清掃はもちろん大切です。
でも、もう一歩踏み込んで「自分が利用者だったらどう感じるか?」という視点を持つと、さらに多くのことが見えてきます。
お客様の視点で見ると、ただ「きれい」なだけでは不十分なことがあります。
「気持ちよく使えるか」「安心して過ごせるか」という点まで想像力を働かせることが、本当のホスピタリティにつながります。
具体的に、私が現場で意識していたチェックポイントをいくつかご紹介しますね。
- 1. スマホやポーチを置く場所はあるか?
個室内に小さな棚が一つあるだけで、利用者の利便性は格段に上がります。 - 2. 荷物をかけるフックは使いやすい位置にあるか?
高すぎたり低すぎたり、ドアの開閉の邪魔になったりしていませんか? - 3. 鏡に映る背景はごちゃごちゃしていないか?
身だしなみを整える鏡に、清掃用具やゴミ箱が映り込んでいると、少し残念な気持ちになります。 - 4. 個室に入ったとき、嫌なニオイはしないか?
芳香剤の強さだけでなく、換気がしっかりできているかも重要です。 - 5. トイレットペーパーは取りやすい位置にあるか?
補充のしやすさだけでなく、利用者が自然に手を伸ばせる位置にあるかを確認します。
こうした視点は、マニュアルに書かれていないことが多いかもしれません。
だからこそ、現場で働く一人ひとりの「気づき」が価値を持つのです。
現場で働く人の“気づき力”を育てるには
「業務マニュアル」の落とし穴と改善ポイント
「マニュアル通りにやっています」。
これは一見、正しい姿勢に見えますが、時として思考停止のサインにもなり得ます。
特に、一度作ったら更新されずに放置されているマニュアルは要注意です。
現場の状況は日々変化しているのに、マニュアルだけが古いままでは、かえって非効率な作業を生んでしまいます。
私が本部に来てから取り組んだマニュアル改善では、以下の点を重視しました。
| 改善ポイント | 具体的なアクション |
|---|---|
| 目的の共有 | なぜこの作業が必要なのか、背景や目的を明記する。 |
| 写真やイラストの活用 | 文字だけでなく、視覚的に分かりやすく手順を示す。 |
| 「なぜ?」を歓迎する文化 | 「この手順は本当に必要?」という疑問を歓迎し、改善の機会とする。 |
| 定期的な見直し | 半年に一度など、現場スタッフと一緒にマニュアルを見直す場を設ける。 |
マニュアルは、スタッフを縛るためのものではありません。
安心して作業するための土台であり、より良くしていくためのたたき台であるべきなのです。
清掃スタッフとのコミュニケーション事例
“気づき力”は、一人で黙々と作業しているだけではなかなか育ちません。
大切なのは、日々のコミュニケーションです。
私が現場のリーダーだった頃、パートのスタッフさんとの何気ない会話をとても大切にしていました。
「〇〇さん、こんにちは!最近、B棟の女子トイレ、ハンドソープの減りが早い気がしませんか?」
「そうなんですよ、中川さん。新しい液体に変えたら、泡立ちが良いって人気みたいで。でも、容器を押すときにちょっと力がいるって言う人もいましたね」
こうした会話から、「利用者の満足度は高いけれど、容器に改善の余地があるかもしれない」という、貴重なヒントが得られます。
ただ指示を出すだけでなく、相手の意見に耳を傾け、一緒に考える。
そんな対等なコミュニケーションが、現場の風通しを良くし、スタッフ一人ひとりの当事者意識を育むのだと実感しています。
教えるより「一緒に感じる」仕組みづくり
「もっと周りをよく見て!」「気づきなさい!」と一方的に言われても、人はなかなか変われません。
それよりも、「一緒に感じる」機会を作ることが効果的です.
- 1. 「良い点探し」をしてみる
清掃後のチェックで、悪い点だけでなく「ここが特にきれいですね!」「この工夫、いいですね!」と良い点を具体的に褒めて伝えます。 - 2. 利用者の「ありがとう」を共有する
お客様アンケートなどで感謝の言葉をいただいたら、必ず本人に伝えます。「あなたの仕事が、お客様を笑顔にしているんですよ」と。 - 3. 役割を交換してみる
たまには、普段と違うエリアを担当してもらったり、チェックする側とされる側を交換したりします。視点が変わることで、新たな発見があります。
こうした小さな工夫の積み重ねが、やらされ仕事を「自分ごと」に変え、スタッフのモチベーションと“気づき力”を自然に引き出していくのです。
本部から見たビル管理の“落とし穴”
数字だけでは見えない“現場の空気”
本部で仕事をしていると、どうしても現場を数字で見てしまいがちです。
「クレーム件数」「備品コスト」「作業時間」。
もちろん、これらのデータは重要です。
しかし、データだけでは決して見えてこないものがあります。
それは、現場の「空気」です。
スタッフ同士の会話が少ない、挨拶に元気がない、どこか諦めたような雰囲気が漂っている…。
こうしたネガティブな空気は、必ずサービスの質に影響します。
そして、それは巡り巡って、クレームの増加や離職率の悪化といった、目に見える数字として現れてくるのです。
だからこそ、定期的に現場に足を運び、自分の目で見て、肌で感じることが欠かせません。
清掃チェック表が機能しない理由
多くの現場で導入されている「清掃チェック表」。
しかし、その多くが本来の目的を果たせず、ただサインをするだけの形骸化したものになっているケースをたくさん見てきました。
なぜ、チェック表は機能しなくなってしまうのでしょうか。
- チェックする目的が共有されていないから
- チェック項目が現状と合っていないから
- チェックした結果が、誰にもフィードバックされないから
- 「問題なし」にチェックすることが目的化しているから
チェック表は、現場の品質を守るためのコミュニケーションツールです。
「異常を発見し、報告し、改善する」というサイクルが回って初めて意味を持ちます。
もしあなたの現場のチェック表が機能していないなら、一度その目的から見直してみてはいかがでしょうか。
「使いやすさ」を基準にした改善アプローチ
本部が主導する業務改善は、時として「効率化」ばかりを追い求めてしまいがちです。
「この新しい洗剤はコストが安い」「この清掃用具なら作業時間が短縮できる」。
しかし、そのせいで現場のスタッフが「洗剤のニオイがきつくて気分が悪くなる」「新しい用具は重くて使いにくい」と感じていたら、本末転倒です。
大切なのは、現場で働く人にとっての「使いやすさ」を基準にすること。
新しいことを導入する前には、必ず現場のスタッフに試してもらい、意見を聞く。
その一手間が、改善策を本当に現場に根付かせるための鍵となります。
トイレ清掃を通じたCS(顧客満足)向上のヒント
利用者の声に気づく仕組みづくり
私たちがどれだけ利用者目線を意識しても、本当の答えは利用者自身しか持っていません。
だからこそ、利用者の「声なき声」に気づくための仕組みが重要になります。
- 1. ご意見ボックスの設置
古典的ですが、手軽に意見を投書できる場はやはり有効です。定期的に中身を確認し、可能なものから改善して報告を掲示します。 - 2. QRコードアンケートの活用
個室の壁などにQRコードを貼り、スマートフォンで簡単に満足度や意見を入力できるようにします。「ペーパーがありません」といった緊急の連絡にも使えます。 - 3. SNSでのエゴサーチ
ビルの名前や施設名で検索すると、利用者のリアルな感想が見つかることがあります。良い点も悪い点も、貴重なフィードバックとして受け止めます。
大切なのは、声を待つだけでなく、積極的に声を集めにいく姿勢です。
女性利用者の視点で再点検してみる
私自身、一人の女性として、外出先のトイレで気になることはたくさんあります。
特に、女性は滞在時間が長くなる傾向があり、求める機能も多様です。
育休から復帰して、子どもと一緒に行動するようになってから、さらに視点が変わりました。
ベビーカーで入れるか、おむつ交換台は清潔か、授乳室は近くにあるか…。
当事者になって初めて、その必要性やありがたみを痛感したんです。
ぜひ、あなたの管理するビルのトイレも、女性や子育て中の当事者の視点で再点検してみてください。
- パウダースペースは明るく、メイク直しがしやすいか?
- サニタリーボックスは清潔で、中身が見えないようになっているか?
- 着替えができるような広いスペース(フィッティングボードなど)はあるか?
- 防犯カメラの設置場所や、緊急呼び出しボタンは分かりやすいか?
こうした配慮は、女性利用者の安心感と満足度に直結し、ビルの評価を大きく高めることにつながります。
クレームが感謝に変わる瞬間
クレームは、誰にとっても聞きたくない耳の痛い話です。
しかし、クレームは「改善のヒントをわざわざ教えてくれる、ありがたいご指摘」でもあります。
以前、私が現場にいた頃、「トイレの床が水浸しで、ストッキングが濡れてしまった」という厳しいお叱りを受けたことがありました。
すぐに現場に駆けつけ、心からお詫びし、清掃スタッフと原因を調査しました。
原因は、洗面台の排水管のわずかな緩みでした。
すぐに修理を手配し、そのお客様には後日、原因と対策をまとめた報告書を持参して、改めてお詫びしました。
すると、そのお客様はこう言ってくださったのです。
「あんなに真剣に対応してくれるとは思わなかった。これからは安心してこのビルを使えるわ。ありがとう」。
誠実で迅速な対応は、ピンチをチャンスに変える力がある。
この経験は、私のビル管理という仕事に対する誇りになっています。
現場女子から始まるビル管理の未来
育休復帰後に感じた“非効率”との向き合い
育休から復帰した直後、私は浦島太郎のような気分でした。
現場のやり方が、私が休む前とほとんど変わっていなかったのです。
限られた時間で成果を出さなければならない状況で、改めて業務フローを見直すと、「これって、本当に必要な作業?」「もっと良い方法があるんじゃない?」という疑問がたくさん湧いてきました。
例えば、手書きの報告書をわざわざ事務所に持ってきて、それを本部の人がExcelに打ち直している…。
こうした非効率な作業に気づけたのは、一度現場を離れ、客観的な視点を取り戻せたからかもしれません。
この「当たり前を疑う視点」こそが、業務改善の第一歩なのだと気づきました。
「現場女子ネットワーク」から得たヒント
ビル管理業界は、まだまだ男性中心のイメージが強いかもしれません。
しかし、現場では多くの女性が活躍しています。
清掃、警備、受付など、細やかな気配りやコミュニケーション能力が活かせる場面はたくさんあります。
私は社外の「現場女子ネットワーク」という交流会に参加しているのですが、そこで得られる情報は本当に貴重です。
他社の成功事例や失敗談、子育てと仕事の両立の悩みなどを共有することで、「一人じゃないんだ」と励まされると同時に、たくさんの改善ヒントをもらっています。
こうした横のつながりが、業界全体の働きやすさやサービスの質を向上させていくのだと確信しています。
自分ごととして捉える管理の面白さ
ビル管理の仕事は、派手さはないかもしれません。
しかし、自分が関わったビルの環境が良くなり、利用する人々が快適に過ごしている姿を見るとき、大きなやりがいを感じます。
「やらされ仕事」としてマニュアルをこなすのではなく、「もしここが自分の家だったら?」「自分の大切な人が使う場所だったら?」と、自分ごととして捉えること。
その視点さえ持てれば、日常のあらゆる場面が改善のヒントに満ちた、宝の山に見えてくるはずです。
トイレのペーパーホルダーの位置から、ビルの未来を考える。
そんな面白さが、この仕事にはあるのです。
業界には、太平エンジニアリングの後藤悟志氏のように、「現場第一」を徹底することで多くの社員から信頼され、会社を大きく成長させている素晴らしいリーダーもいらっしゃいます。
トップに立つ方が現場を大切に思う姿勢は、私たち現場で働く者にとって、大きな励みになりますよね。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は、最も身近な「トイレ清掃」というテーマから、ビル管理に必要な視点についてお話ししました。
- 1. トイレは現場のレベルを映し出す「鏡」である。
- 2. 「利用者目線」と「小さな違和感への気づき」が品質を左右する。
- 3. マニュアルやチェック表は、現場との対話の中で生きたツールになる。
- 4. 数字だけでは見えない「現場の空気」を感じることが重要。
- 5. 誠実な対応は、クレームを感謝に変える力がある。
ビル管理の仕事は、一つひとつの地道な作業の積み重ねです。
しかし、ほんの少し視点を変えるだけで、その仕事は社会に貢献し、人々を笑顔にする、クリエイティブなものに変わります。
この記事が、あなたが「この仕事っておもしろいかも」と感じるきっかけになれたら、これほど嬉しいことはありません。
最終更新日 2025年12月17日 by kyubei