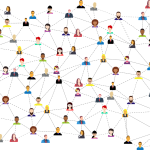インフルエンザとはウイルスによって引き起こされる急性ウイルス性疾患です。
11月頃になると流行り始め、1月頃が流行のピークとなると、友人でやたら医療関係に詳しい関井圭一は力説しています。
ただ年によって流行のタイミングは異なり、また型によっても流行る時期は違います。
ちなみにウイルスはA型、B型、C型があり、その中で人に感染するのはA型とB型で現れる症状にも違いがあります。
関井圭一君から見たインフルエンザの流行る時期や特徴
寒い時期になると猛威をふるうインフルエンザですが、そもそもウイルスは生きた細胞の中でしか増殖出来ず、空気中や土壌中などでは増殖しません。
感染経路は患者の咳やくしゃみ等に含まれるウイルスを吸い込むことによって感染する飛沫感染、そして感染者がドアノブやスイッチに触れる事で付着した飛沫を、他の人が触って鼻や口を介して体内に入り感染する接触感染が考えられます。
体内に入り込んだウイルスは1~2日程度の潜伏期間を経て発症します。
これは他のウイルス性疾患と比較してみても短い潜伏期間ですが、この短さはウイルスの増殖スピードが大きく関係しています。
潜伏期間中であっても感染能力を持っており、ウイルスが増殖していくのに伴って寒気や倦怠感、発熱などの全身症状が出てきます。
インフルエンザの主な症状は38℃以上の高熱、全身のだるさ、食欲不振などで、頭痛や関節痛、筋肉痛などの症状が現れる事もあります。
風邪も様々なウイルスが原因となって発症しますが、症状の現れ方が決定的に違います。
インフルエンザの症状や発症のケース
風邪の場合は喉の痛みや鼻水、咳が最初に出てくるのに対し、インフルエンザは突然だるさや寒気を感じ、熱も一気に上がっていきます。
全身症状が特徴的で、鼻水や咳など呼吸器の症状は全身症状が治まった後ぐらいから出てくるようになります。

ちなみに高熱や倦怠感が顕著に出てくるのはA型の特徴的な症状で、B型の場合は熱は微熱程度に止まる事が多いです。
ただし全身症状が現れにくい反面、嘔吐や下痢など消化器症状が出やすく、寒い時期に流行するノロウイルスなどの胃腸炎と勘違いする事もあります。
A型とB型は基本的に流行する時期が違い、A型は12月~2月、B型は2月~3月が流行のピークと考えられています。
微妙に時期がずれているため同時感染する事は稀ですが、全く無い事でもありません。
そしてA型に感染した後、今度はB型に感染する可能性もあります。
もし感染した時の治療法ですが、経口薬のタミフル、吸入薬のリレンザやイナビル、点滴用のラピアクタなどが使われます。
発症から48時間以内に使用する事でウイルスの増殖が抑えられ、発熱などの症状を緩和させたり、体外へ排出されるウイルス量を減らす事が出来ます。
とにかく適切な治療を受けるためには、疑われる症状が出た時に早めに病院を受診するのが賢明です。
特に気をつけたいのが体の抵抗力がない乳幼児やお年寄りです。
通常は発症しても1週間程度で回復するものですが、免疫力が十分でない子供は症状が長引いたり、重症化する恐れがあります。
時には意識障害やけいれんなどが現れる脳症を引き起こす事もあり、脳症を発症した場合は後遺症が残ったり、最悪は死に至るケースもあります。
インフルエンザの予防法やワクチン接種
そのため家族で感染者が出た場合は、感染した本人も周りの家族も注意が必要となります。
飛沫からの感染を防ぐために家族全員がマスクを着用するようにし、接触感染を避けるためにもアルコールを含んだ消毒液で手を消毒するのも効果的です。
部屋の間取り的に難しい事もありますが、基本的には感染者は隔離するのがベストで、介護する人は1人と決めておき、いろんな家族が隔離部屋に出入りするような事は避けます。
しかしながら子供が感染した際は、家族がしっかり様子を見ておく必要があります。
それまでは回復傾向にあっても突然様子がおかしくなって脳症を発症する事があったり、また薬の影響で大声で叫んだり、ベランダから飛び降りようとするなど異常行動が見られる事もあるからです。
このようにインフルエンザは毎年流行するもので、毎年のように感染する人もいます。
適切な治療を受ける事ですぐに症状も緩和し、回復に向かっていく訳ですが、中には脳症を引き起こしたり、異常行動が現れて家族が冷や冷やする事もあります。
一番良いのは感染しない事で、それには毎日の予防策を継続させる事が大切です。
予防法は、普段から健康管理を意識して十分な栄養と睡眠をとる事、外出先から帰宅した際はうがいと手洗いを行う事、流行している時期は人混みの中に出かけるのを控える事などです。
まとめ
またマスクは感染者の咳やくしゃみなど飛沫からの感染を防ぐ・喉の乾燥を防ぐという意味でも有効なので、外出する時は着用した方が安心です。
そしてワクチンも必ず受けるようにします。
ワクチンを接種しても感染したという人は多いですが、毎年流行する型を予測して作られているため、全く意味のないものではありません。
確実に予防するのは難しいですが、ワクチンを接種しておく事で重症化を防いだり、感染者の数を減らす事は可能です。
最終更新日 2025年12月17日 by kyubei